この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
- アコギの部品名称を知りたい
- 各部品の役割を知りたい
楽器店に行った際に、店員さんに専門用語を言われてもわからない、ギター雑誌で出てくる用語がわかない人は多いです。
この記事を読むことで、各部の名称を知ることができます。
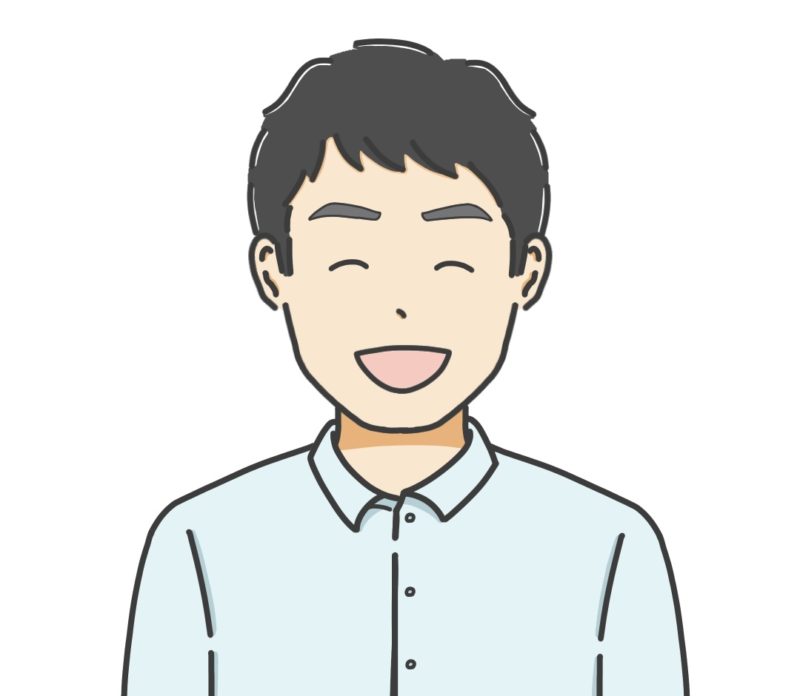
ギター購入時に役立ったり、修理時にお店の人に状態を伝えられるようになるよ。
ヘッド部

ヘッド本体
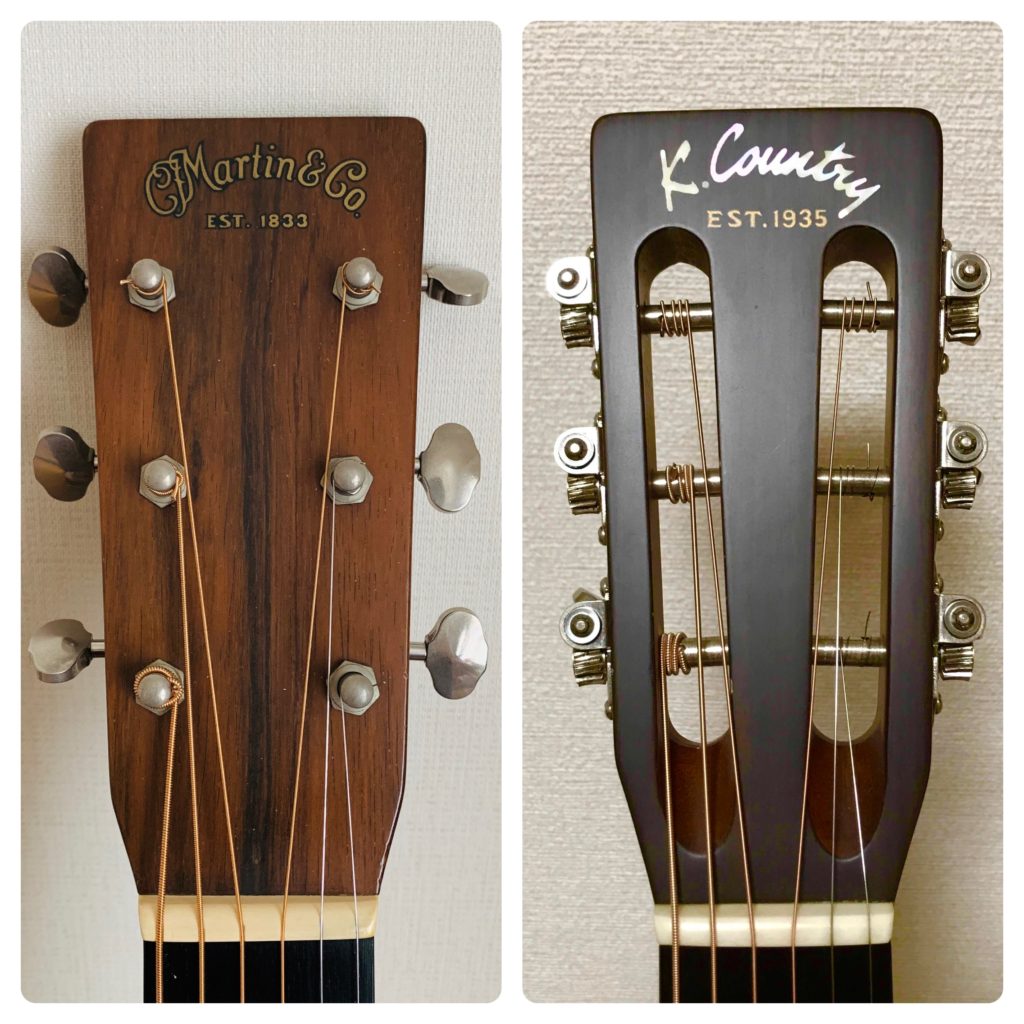
- 左:通常ヘッド
- 右:スロッテッドヘッド
アコースティックギターのヘッドは2タイプあります。
スロッテッドヘッドと呼ばれる形状は、クラシックギターに見られるタイプで、アコギで採用しているメーカーは少ないです。
単純にデザインだけの違いだけではありません。
通常ヘッドは、ペグポストに対して、上下に弦が巻かれますが、スロッテッドヘッドはペグポストに対して左右に巻かれます。
上下に巻けばナット付近の弦の角度が変わり、弦との摩擦が増すことになります。
結果、弦が切れやすくなります。
つき板(デザイン)

ヘッド表面を「つき板」と呼び、別素材を貼り付けることで、様々な木目やインレイのデザインを可能とします。
ヘッドのデザインはメーカー、個人製作家が個性を出す部分です。
量産メーカーより、個人制作家の方が個性的なデザインが多いです。
ヘッドの美しさでギターを選ぶ人もいるほどです。
GrevenやWater Road Guitarsはインレイが美しいのが特徴です。
ペグ(糸巻)


- WAVERLY(ウェイバリー)
- SAHALLER(シャーラー)
- GROVER(グローバー)
- GOTOH(ゴトー)
- KLUSON(クルーソン)
ペグは回す部分、つまみと認識されていますが、「ペグポスト」「弦穴」「ペグシャフト」など総称して呼ぶことが多いです。
その他に「チューナー」「チューニングメーター」「チューニングキー」と呼ぶこともあります。
プラスチック製のペグは、ストリングワインダーを使うと割れる可能性があるので注意が必要です。
オープンバックペグ
ヴィンテージギターに多く見られ、歯車部にカバーが無く、剥き出しになっているタイプです。
カバーが無いため、ペグの重量が軽く音抜けが良い傾向があります。
ホコリが溜まりやすく、グリスが固まり、動きが悪くなることがあります。
ロトマチックペグ
アコースティックギターに多く採用されるタイプです。
重量が重く、太いサウンドとサスティーンが良くなります。
カバーで完全に覆われており、ホコリが入らないのがメリットです。
クルーソンペグ
重量が軽いため、サスティーンは短めで、ギター本来の鳴りを楽しめます。
よく見ると小さな穴が確認できますが、穴からメンテナンス時に潤滑剤(油)を入れてやります。
実際はカバーを開けて行なった方が良いです。
3連ペグ
古いギターに見られるタイプで、金属ベースにペグが付いているのが特徴です。
ヴィンテージのGibsonによく見られます。
ダイヤモンド・ヴォルート(ボリュート)

接着部の強度を上げるための仕様です。
Martinによく見られる仕様で、ヘッドとネックの間(裏)に凹凸があります。
昔、Martinはネックとヘッドを別々に作り接着していました。
現在、ネックは1ピースで作られるようになりましたが、デザインの1つとして残っています。
1Pネックでもダイヤモンド・ヴォルート(ボリュート)があった方が強度は上がります。
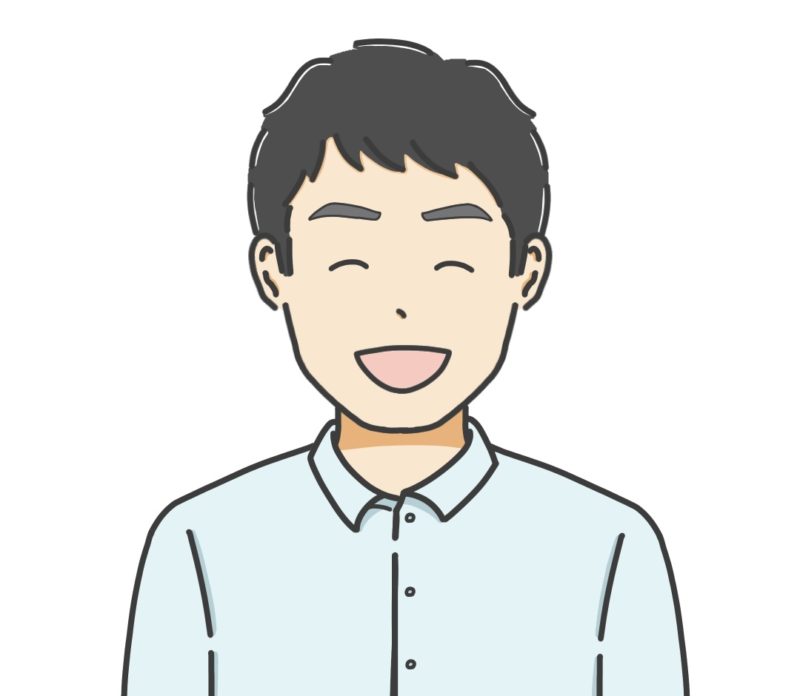
強度が上がったと言っても、折れるときは折れるから、ギターは大事に扱ってね。
トラスロッドカバー

カバーを開けると、トラスロッドが入っており、回すことでネックの反りを調整できます。
※調整には六角レンチが必要です。
全てのギターにカバーがあるわけではありません。
ギターの多くはサウンドホール側からトラスロッドを調整します。

サウンドホールから覗いて、トラスロッドがある場合はトラスロッドカバーは「ダミー」になります。
YAMAHAのFGシリーズに多く見られます。
ナット

- プラスチック
- 牛骨(牛の骨)
- ビンテージボーン(牛骨のオイル漬け)
- タスク/TUSQ(人工象牙)
- ブラス(真鍮)
- デルリン(樹脂製品)
- カーボン
- 水牛
素材によって、サウンドに大きく影響する大事な部分です。
ナットは消耗品のため、溝の深さや角度によってサウンドが変わったり、チューニングした際に「キーン」と音が鳴ったりします。
安価ギターのほとんどが「プラスチック製」になります。
ギターの価格が上がれば「牛骨」「TUSQ」になっていることが多いです。
サウンドを向上させるために、素材を変更することもできます。
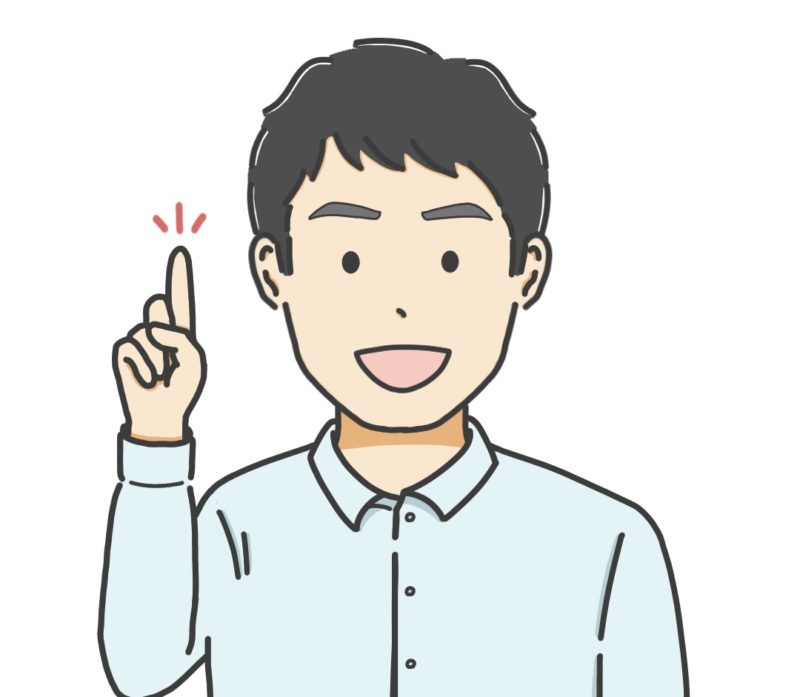
ナット自体は簡単に手に入るけど、取り付けがシビアだから、楽器店にお願いした方がいいよ。
ネック部
ネック

- マホガニー
- メイプル
ネックは「ネック」+「指板」2つを合わせて呼ばれることが多いです。
ネックの上に指板が乗っていることになります。
指板は柔らかいため、弦の張力や湿度で反ることがあります。
ネックスケール
ネックの長さはギターによって異なります。
間違いやすいのは「ネック」の長さではありません。
ネックスケールは「弦の張られてある長さ(ナットからブリッジの長さ)」になります。
指板(フィンガーボード)
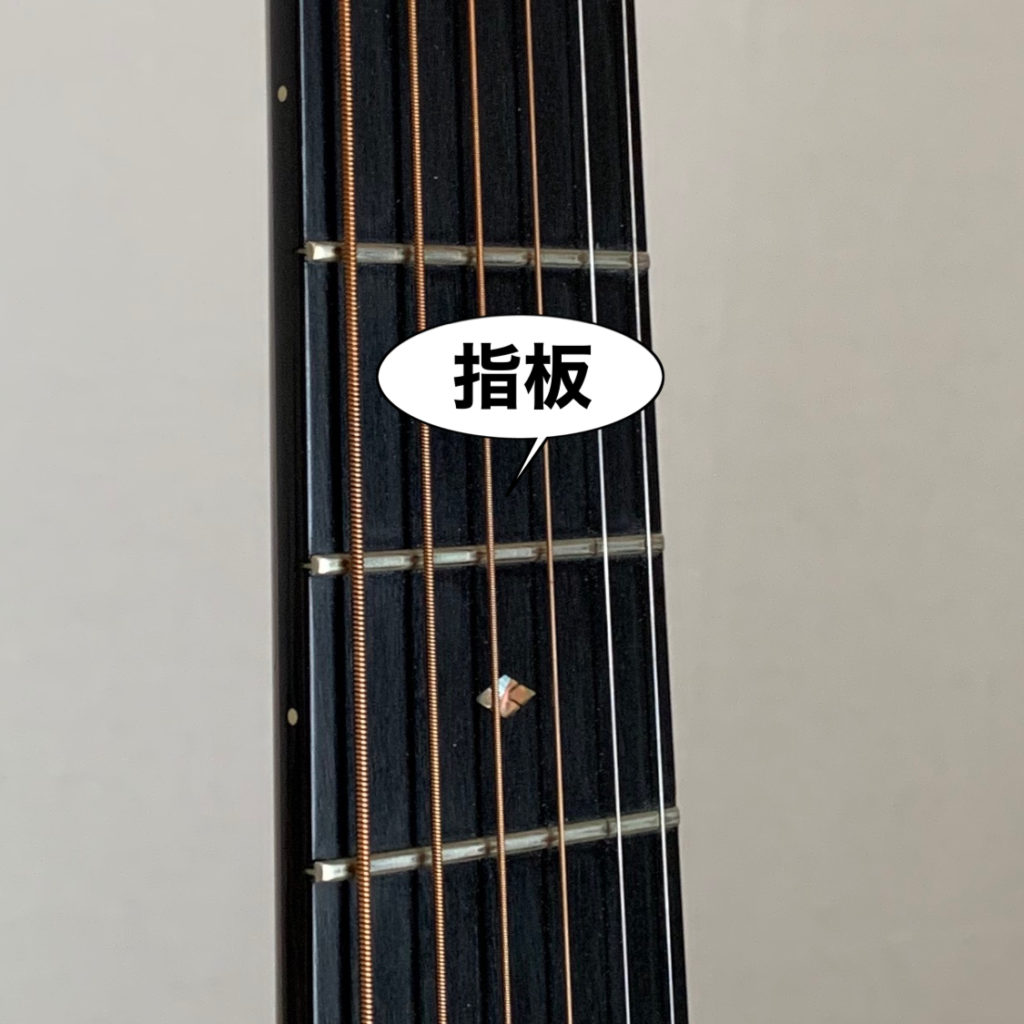
- ローズウッド
- エボニー
- メイプル
ローズ指板、エボニー指板は未塗装で、湿度の影響を受けやすいです。
冬場の乾燥する時期になると、木が痩せてフレットが飛び出したり、指板が割れることがあります。
指板の保湿対策はオレンジオイルなどを使うことです。
※メイプル指板は塗装されていることがほとんどで、オレンジオイル等を使用すると、逆に塗装を傷めることになるので注意してください。
ポジションマーク

ポジションマークは、演奏性を向上させるための目印です。
メーカーや個人製作家によって「全く無いもの」「12フレットのみ」などパターンは無数にあります。
デザインも「ドット」「スノフレーク」「バード」「ツリー・オブ・ライフ」など様々です。
サイドポジションマーク(サイドドット)
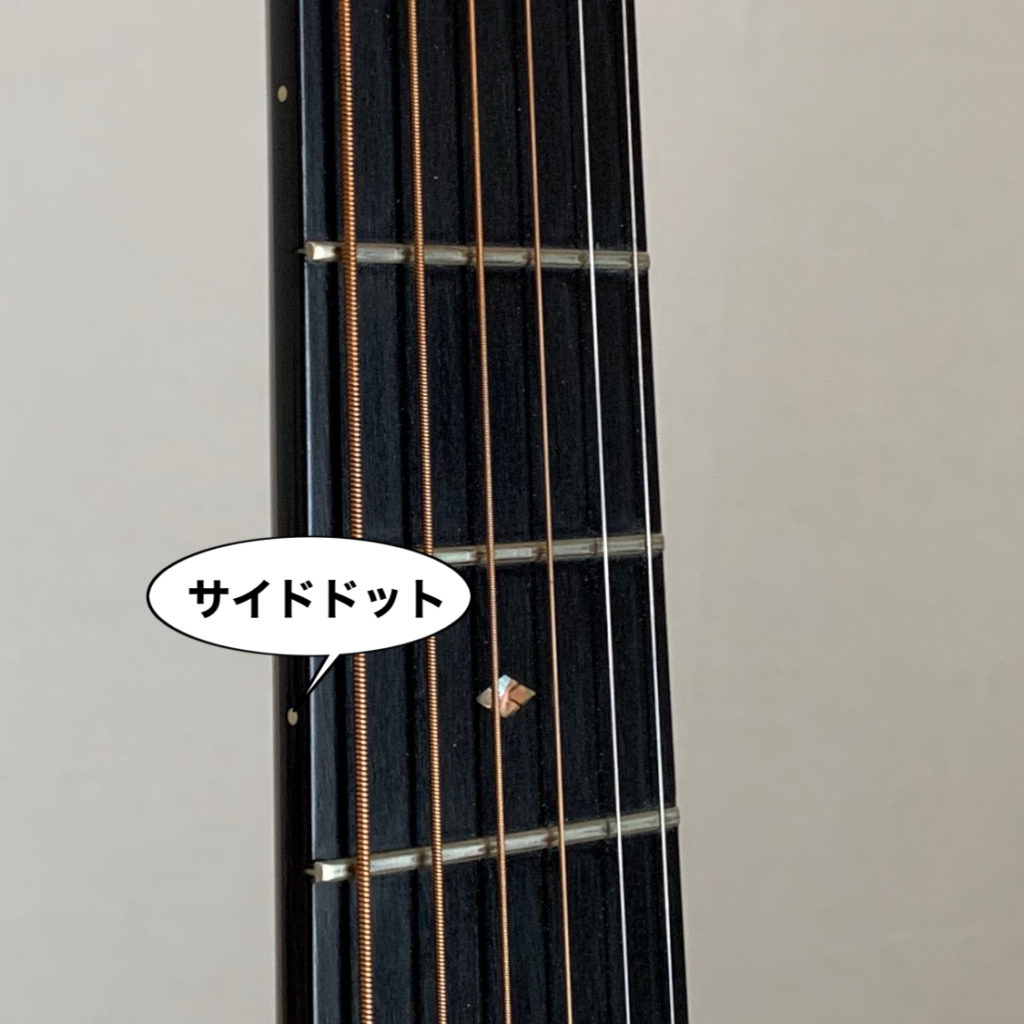
指板上にポジションマークが無い場合に、補助するのがサイドポジションマーク(サイドドット)です。
立って演奏する場合に役立ちます。
フレット
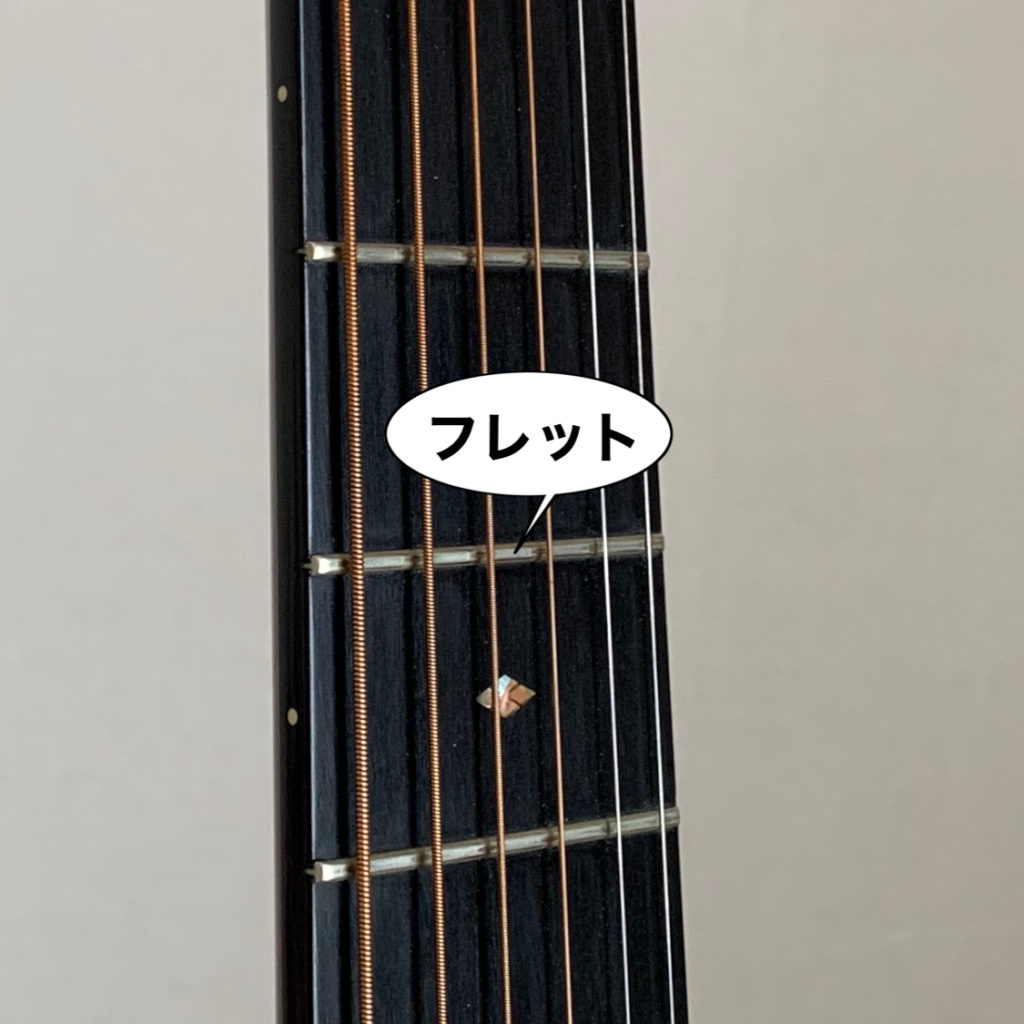
- ニッケル:柔らかく減りやすい
- ステンレス:ほぼ減らない
フレットは金属のバーのことです。
国産、海外産によってフレットの形・サイズが異なります。
フレットが減った場合は「擦り合わせ」「フレットの交換(打ち直し)」が必要になります。
フレットが錆びると演奏性が悪くなるため、半年〜1年を目安にフレットを磨くのがオススメです。
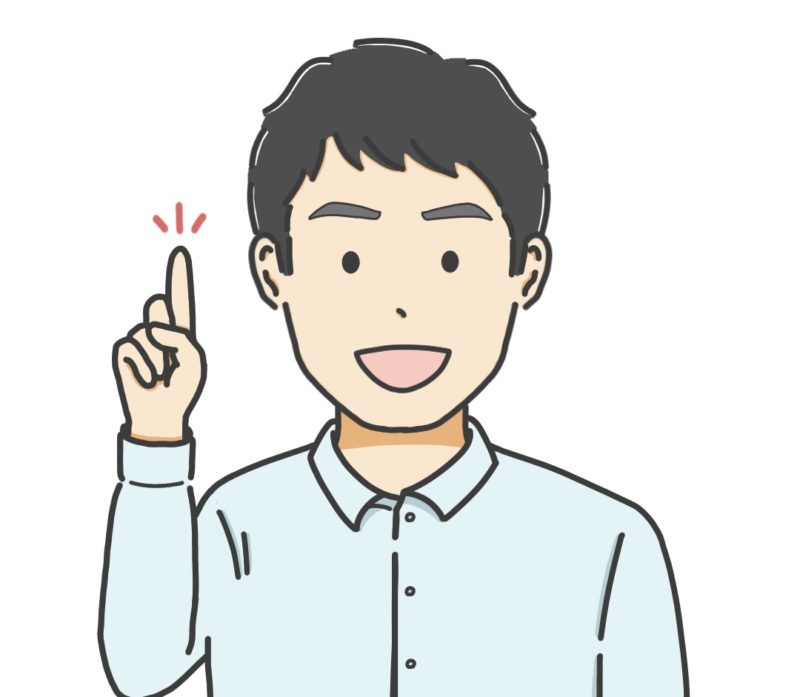
「フレットバター」は拭くだけで錆を落とせるから便利だよ。
ネックヒール(キャップ)

ヒール
画像のギターは「ヒール」が緩やかになっていますが、より鋭角になるとハイポジションが弾きやすくなります。
通常のアコギは、頑張っても15フレットくらいまでしか指が届きません。
弾き語りではハイポジションを使うことはありませんが、ソロギタースタイルによっては使用されます。
ストラップピン
通常、新品のギターにストラップピンはありません。
ライブでストラップを掛けて演奏したい場合に増設します。
増設は、改造扱いになり、楽器を売る時に多少の値落ちがある場合があります。
ネックブロック
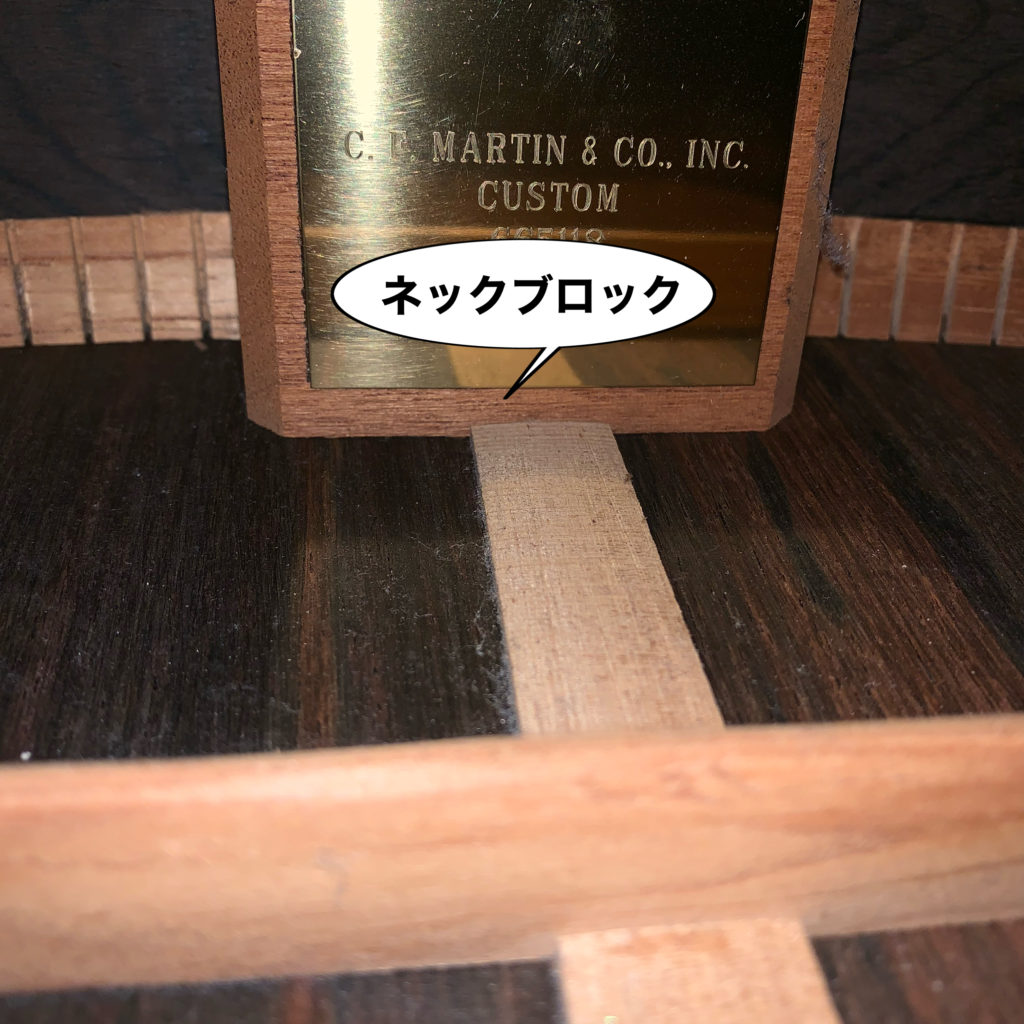
ネックとボディの結合部分です。
メーカーによっては、シリアルナンバーが刻印されています。
ネックジョイント

- 12Fジョイント:音が太く豊かな鳴り
- 14Fジョイント:タイトで歯切れの良い鳴り
ヒールとネックブック周辺(結合部分)をジョイントと呼びます。
昔、アコギやクラシックギターは「12フレットジョイント」が普通でした。
徐々に「14フレットジョイント」に移行していきます。
現在のほとんどのギターは「14フレットジョンイト」で作られています。
「12フレットジョイント」が全くないわけではなく、Martinの小型ボディ(O、OO、OOOシリーズ)に一部存在します。
ボディ(トップ)

トップ(表板)
- アディロンダックスプルース
- ジャーマンスプルース
- イングルマンスプルース
- イタリアンアルパインスプルース
- シトカスプルース
- えぞ松
- シダー
グレード
トップ材はセンサーなどで基準が付けられ、グレード分けされています。
グレード基準は非公開が多いです。
ベアクロウ
スプルースに見られる、クマの爪でひっかいたような木目を意味します。
ロゼッタ
貝仕様やウッド仕様などギターによって様々なパターンがあります。
ピックガード
弾いた時にピックキズや爪キズから守るもので、形状や色も沢山あります。
※新品のギターを購入した時は透明なフィルムが貼られてあります。
交換する場合
ピックガードは楽器店やネットショップで販売していますが、個人が簡単に交換できる物ではありません。
ピックガードはボディに接着されているので、熱を加えてゆっくり剥がす必要があります。
交換する場合はプロに任せましょう。
塗り込みピックガード
Martinギターに見られるもので、ピックガードの上からラッカー塗装した仕様です。
ピックガードは経年変化し縮みます。
結果、トップ板が引っ張られることで塗装割れが発生します。
ラッカー塗装とは?
正式名称:ニトロセルロースラッカー
塗装が薄いので、音の「鳴り」が良いとされますが、施工に手間がかかるため、高級ギターに使われることが多いです。
とてもデリケートな塗装のため、取り扱いが難しいとされています。
温度や湿度などで白濁したり、ゴムと化学反応を起こし、ゴム焼け(黒くなる)することがあります。
バインディング

- プラスチック(セルロイド)
- アイボロイド(象牙模様)
- ヘリンボーン(ニシンの骨模様)
- アバロン(メキシコ貝)
- べっ甲
- ウッド(黒檀・メイプル)
バインディングはボディを守る役割を持っています。
主にトップ、サイド、バック、ネックジョイント部で使われることが多いですが、ネック部やヘッド部にも使われています。
Martinの40シリーズは、貝のキラキラしている見た目に誰もが憧れます。
※貝の種類によっても光り方が異なります。
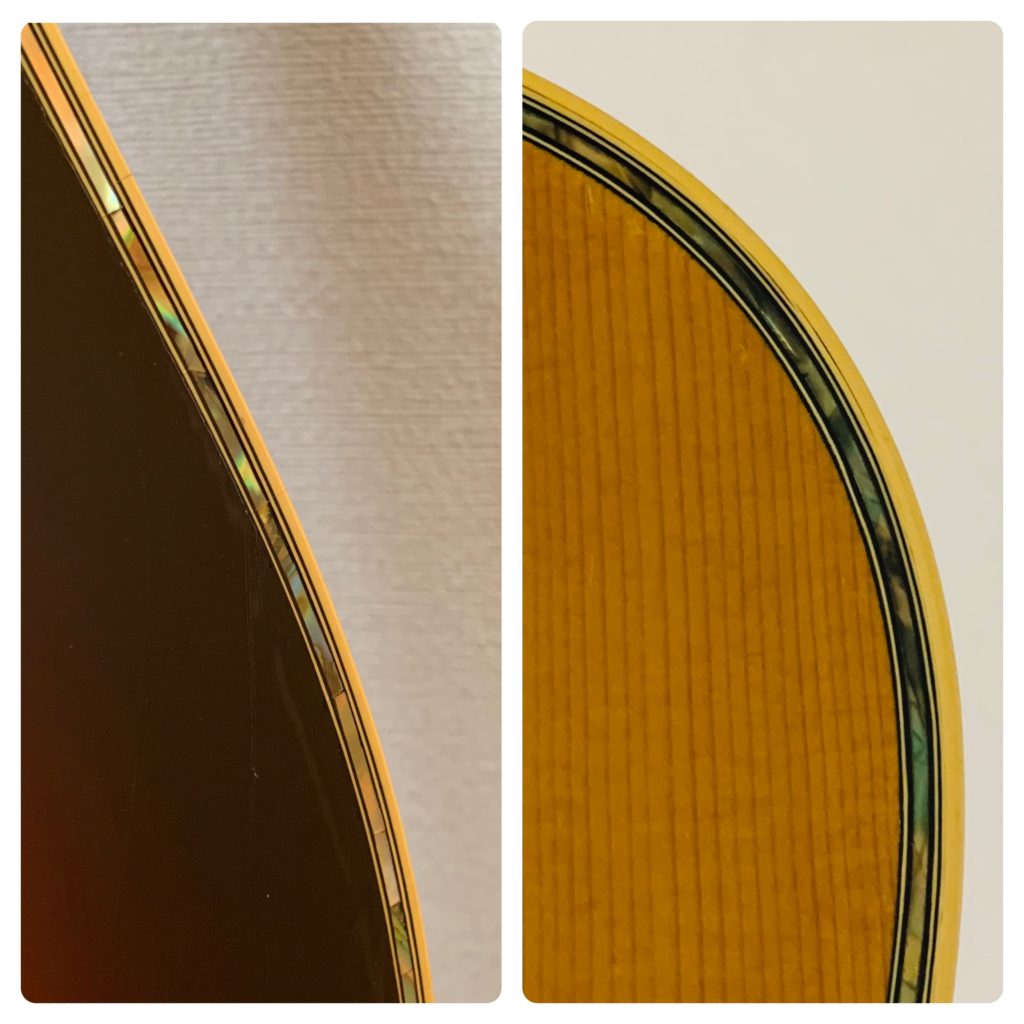
本物(左)と偽物(右)
安価なジャパンヴィンテージギターに多く採用されているのが、アバロン風の仕様です。
貝が入っている様に見えますが、間近で見ると貝でないことがわかります。
パーフリング
バインディングと同じ扱いにされることが多いです。
違いはバインディングより「内側にあるデザイン仕様」のことを言います。
カッタウェイ

ボディを削った様な加工です。
メリットはハイポジションまで手が届くことです。
カッタウェイ有と無では音量が違うと言われますが、そもそもボディ面積が少ないのでそれは事実です。
カッタウェイ加工のギターは、電気を通してアンプから音を出すことができるモデルが多いです。
アンプから音を出せば音量問題は解決できます。
エンドピン

ギターのストラップを付けるためのピンです。
エレアコの場合はエンドピンを抜いて、シールドを挿せる「エンドピンジャック」を取り付けることになります。
サドル

- プラスチック
- 牛骨(牛の骨)
- タスク/TUSQ(人工象牙)
- ミカルタ(樹脂)
弦の振動をギターに伝える大事な部品です。
アジャスタブルサドル
1960年台のGibsonギターに見られる仕様で、高さを変えられるサドルです。
ロングサドル
Martinギターに見られる通常より長いサドルです。
メリットはブリッジとの接触面が大きくなるので、弦のサウンドをより多く効率良く伝えることができます。
ブリッジ

ボディトップに接着され、弦の振動をギターに伝える大事な部品です。
アコギは弦の張力が約70kgとされています。
そのため張力で「トップ膨れ」「ブリッジ剥がれ」のトラブル起きやすいです。
ブリッジピン

- プラスチック
- 牛骨(牛の骨)
- タスク/TUSQ(人工象牙)
- エボニー(黒檀)
- ブラス(真鍮)
- カーボン
- 水牛
弦を固定するピンで、長年使用していると消耗してきます。
楽器店で簡単に手に入るため、手軽にカスタマイズできる部品です。
先端にアバロン(貝)が入っているピンもあるため、見た目の変化を楽しむことができます。
エボニーなど天然素材のピンは柔らかいので「ブリッジピン抜き」を使うと削れるので注意が必要です。
ボディ(サイド・バック)

サイド・バック(側板・裏板)
- ブラジリアンローズウッド
- インディアンローズウッド
- マダガスカルローズウッド
- ホンジュラスローズウッド
- ココボロ
- メイプル
- マホガニー
- サペリ
- コア
トップ材より様々な材が使われることが多いです。
特にブラジリアンローズウッド(ハカランダ)仕様のギターは人気です。
ワシントン条約で伐採、輸入が厳しく規制されているため、年々価格が高騰しています。
2Pと3P
ギターのバック材は、2枚板(2ピース)で制作されることが多いですが、中には3枚板(3ピース)の仕様もあります。
代表機種はMartinのD-35です。
3枚板の中心を別素材で挟む仕様です。
柾目と板目
ギターの価値的には、板目より柾目の方が高い傾向があります。
柾目は太い丸太の中心でしか取れません。
しかしそれでは材がもったいないので、その外側(板目)もギター材として使われます。
結果、採取できる量が少ない「柾目」の方が良い材とされます。
木目が真っ直ぐなものは、乾燥時の伸縮性が安定していると考えられています。
実際、音にはそこまで変化がないようです。
バックストリップ
ボディバックに縦に入っているデザインのことを言います。
サウンドには影響ありません。
ブリッジプレート
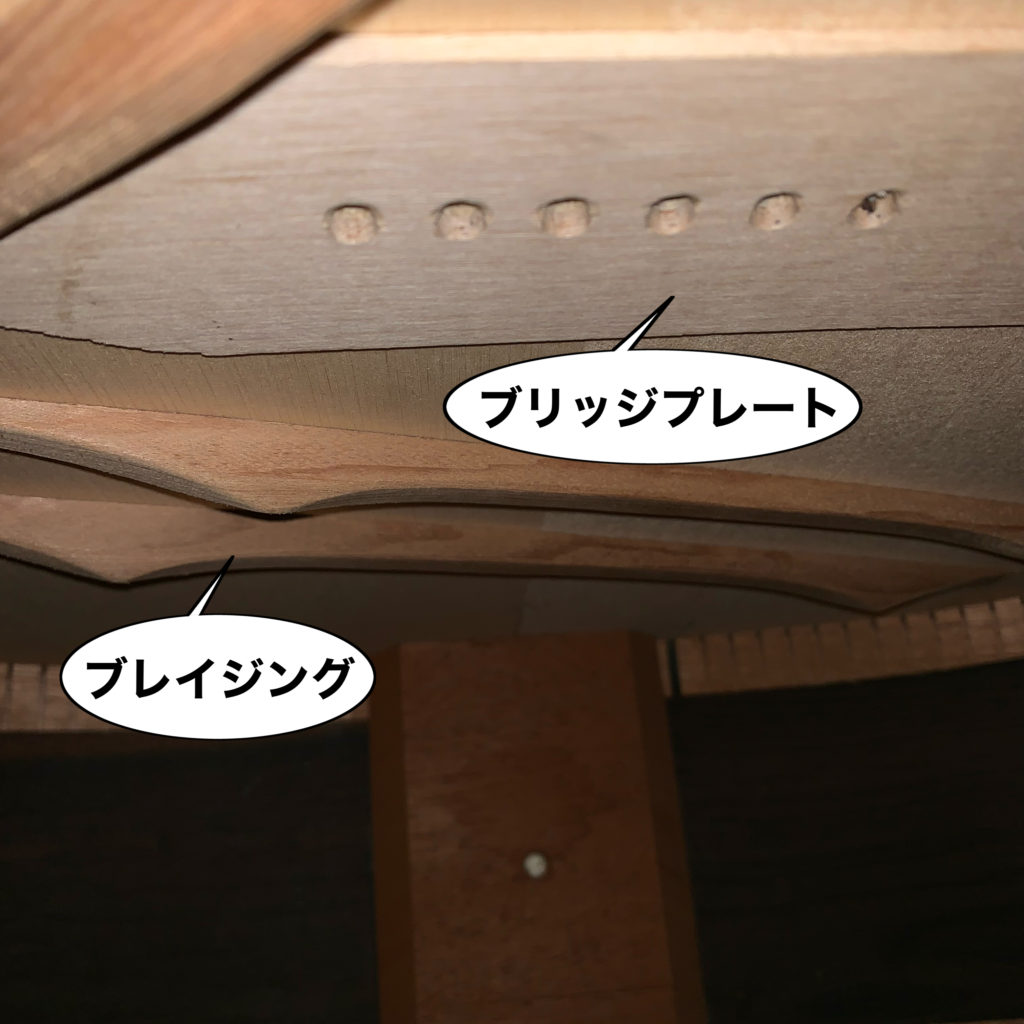
弦を固定するプレートの名称です。
長年使用すると破損する場合があります。
弦交換時に鏡などで、定期チェックするしか方法はありません。
ブレイシング(ブレーシング)・力木
- Xブレイシング
- スキャロップドブレイシング
- フォワードシフトテッドXブレイシング
- ノンスキャロップドブレイシング
ブレインシングはサウンドに大きく影響する部分になります。
プリアンプとバッテーボックス
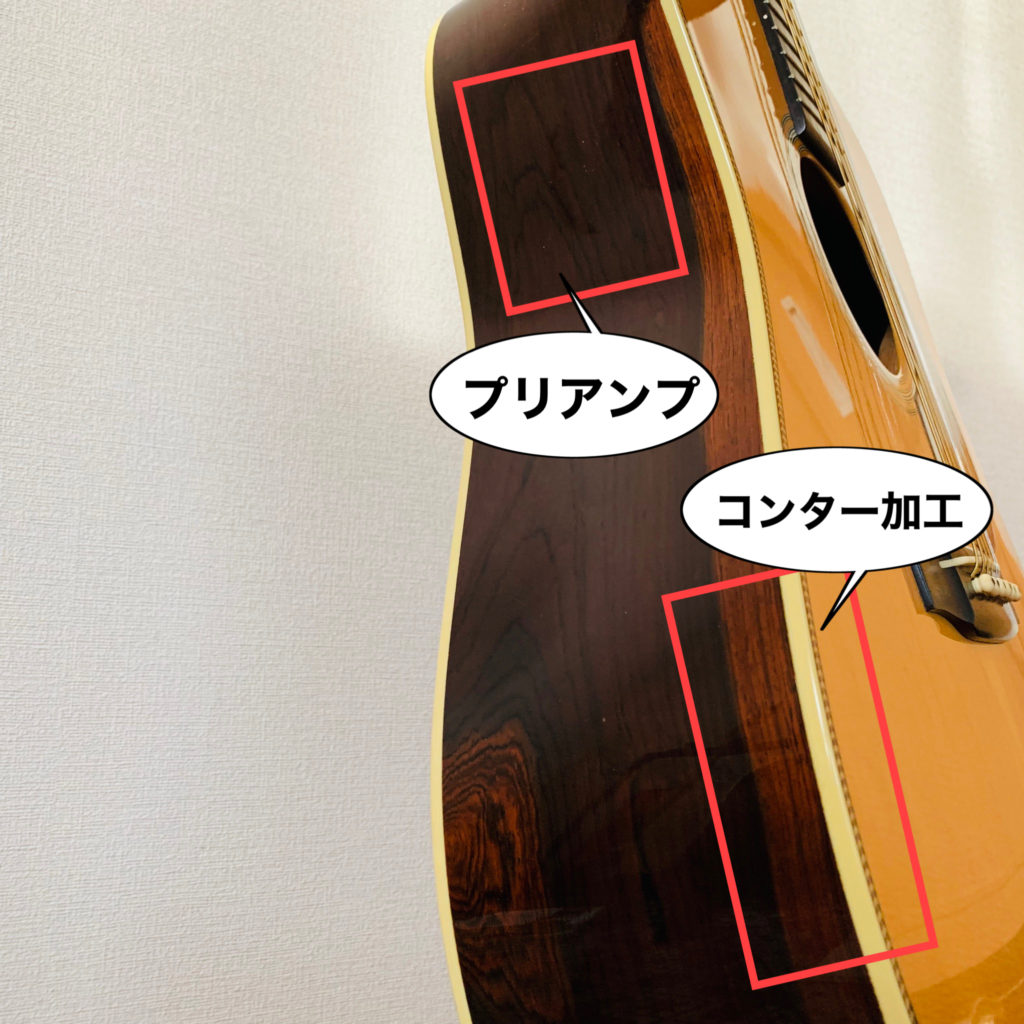
※プリアンプとバッテーボックス搭載のギターを所有していないため、搭載位置に印を付けています。
プリアンプ
エレアコに搭載されている物で、イコライザーやチューナー機能を搭載して機種もあります。
バッテリーボックス
プリアンプを搭載しているギターにはセットで付いています。
搭載位置はヒール部やギター内部のブロック部にあることがほとんどで、9Vバッテリーを使います。
コンター加工
肘が当たる部分が削られていることで、長時間弾いても疲れにくい効果があります。
採用しているメーカーは少ないです。
台湾・ベトナム製のAyersギターに多く見られる加工です。
まとめ

今回はアコギの各部品を解説しました。
部品は素材や状態によって、サウンドに大きく影響します。
「弾きやすいギター」「良い音のギター」は自分で作ることができます。
安価なギターに多い、プラスチック部品(ナット、サドル、ブリッジピン)を牛骨やタスクに変えるだけで、音質が向上します。

各部品の役割を覚えて、少しずつ手を加えていくのも面白いよ。
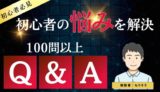 ギター初心者の悩み(あるある)を解決【Q&A100個】
ギター初心者の悩み(あるある)を解決【Q&A100個】 





